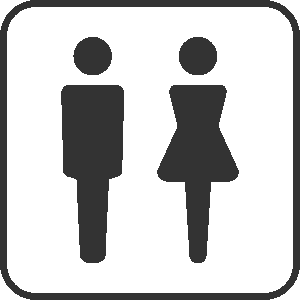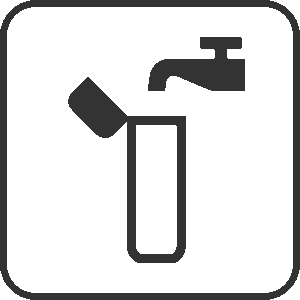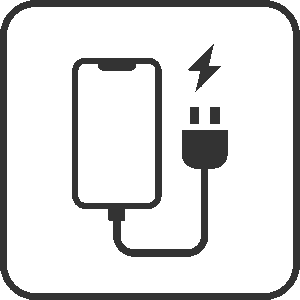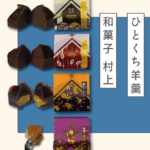素通りしがちな駅。特に金沢駅は観光地から離れており、移動の手段として、お土産を買う場所として”使う”人が多い。だが、金沢駅は伝統工芸がいたる所にちりばめられている。工芸や美術が好きな人には、美術館として”訪れる”のもおすすめ。そんな美術館としての金沢駅の魅力を紹介していきます。
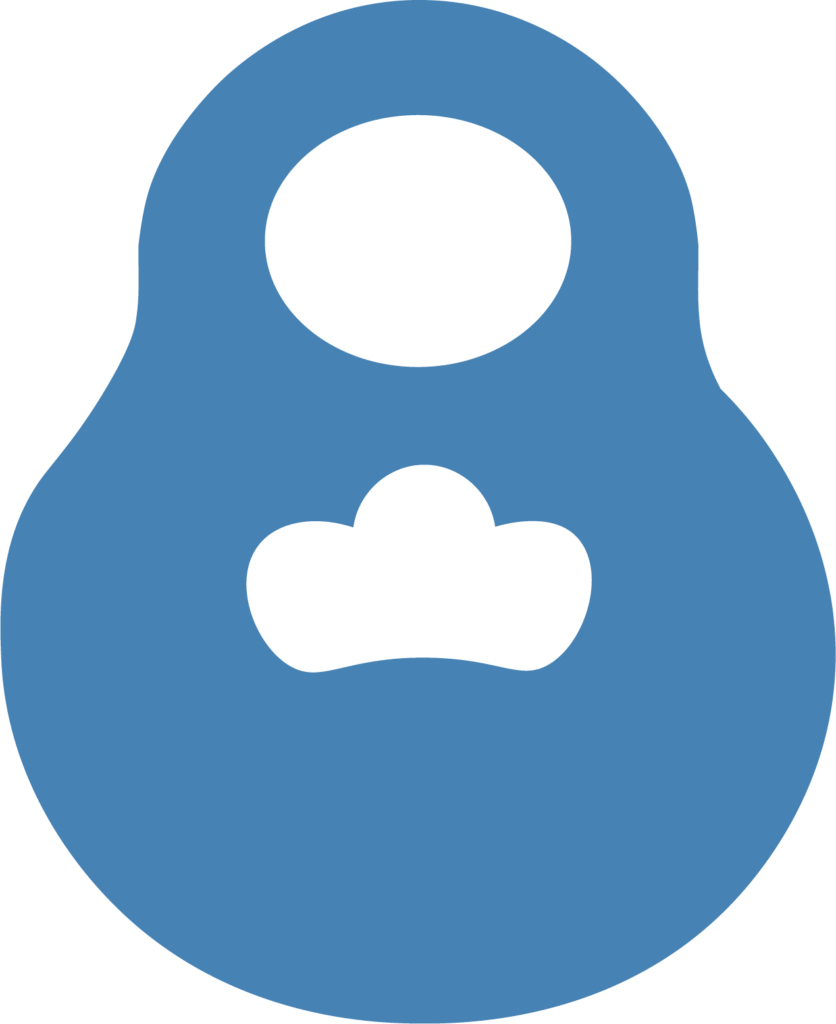
昼も夜も魅力な鼓門

金沢駅と言えば駅前にたたずむ鼓門。金沢の伝統芸能である能楽の鼓をイメージした、壮大な木造建築。その高さは約13メートルで、金沢駅で際立つ存在になっています。また、夜になるとその美しさはより一層増します。日没からは金沢にちなんだ色で彩られ、神秘的な雰囲気も楽しめる。土日には、金沢の伝統色である加賀五彩が2分毎に変化。平日の毎時00分からの2分間、曜日ごとに加賀五彩に彩られる。月曜日は臙脂(えんじ)、火曜日は藍、水曜日は草、木曜日は黄土、金曜日は古代紫。到着してすぐの昼の鼓門も魅力ですが、人気が少ない23時頃の鼓門は静かで神秘的。そんな夜の鼓門もおすすめです。
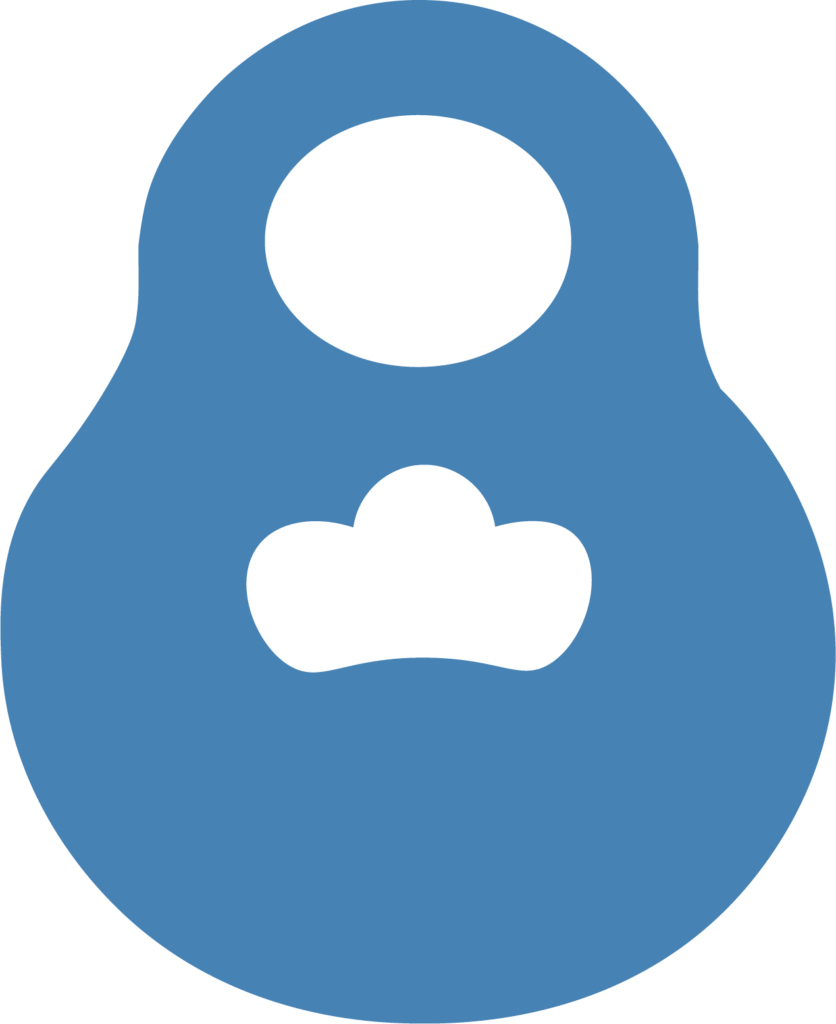
お出迎えのもてなしドーム

金沢駅を出てすぐ、まず目につく巨大なガラス天井が特徴のもてなしドーム。約3,000枚ものガラスでできたドームは、金沢のもてなしの心が込められている。1年の半分以上、時には3/2以上が雨天の金沢。もてなしドームは、そんな雨の多い金沢を訪れる人たちに、傘を差しだすコンセプトで造られいている。モダンな造りをしているもてなしドーム、対称的な伝統と木で造られた鼓門とのコントラストが建築の美しさを醸し出します。
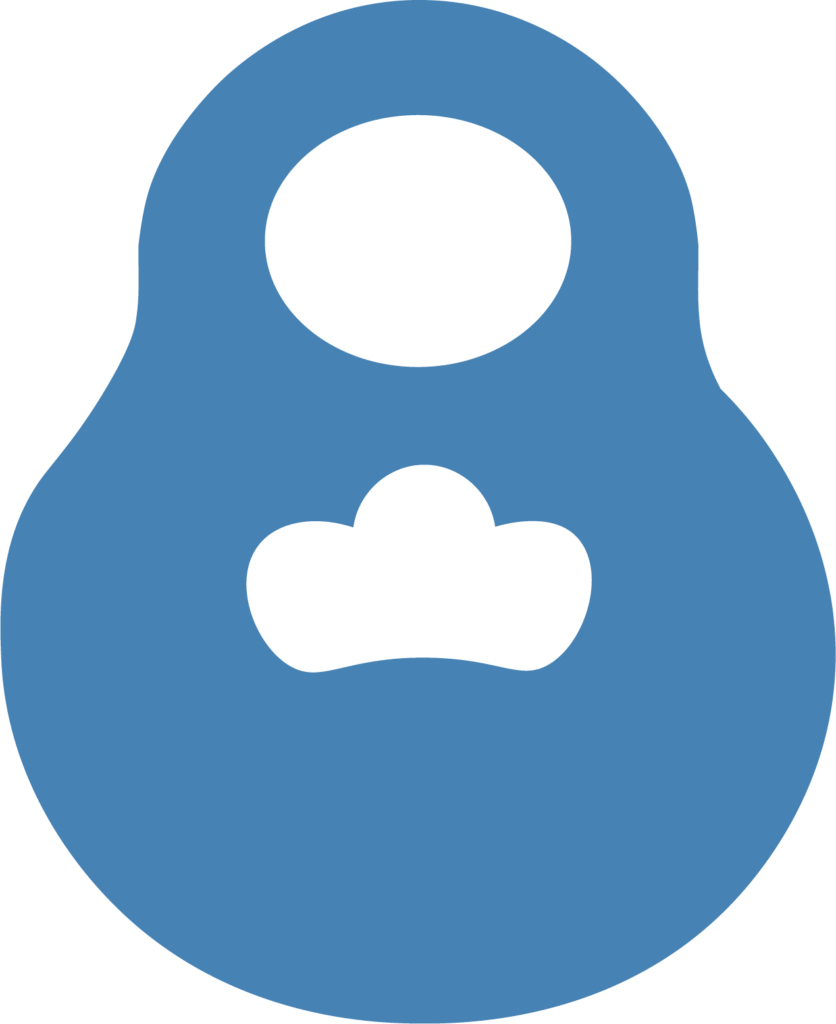
柱に溶け込められた伝統工芸

美術館とも言える金沢駅。その特徴のひとつでもある、コンコースの柱たち。コンコースは素通りしがちですが、金沢駅は人間国宝の作品も飾られている贅沢な場所。その門柱には、金沢だけではなく、工芸王国ともいわれる石川県を代表する作品が24点集まる。輪島塗や九谷焼、金沢漆器などの工芸品が掛け軸のような縦型のプレートで飾られている。他にも、コンコース内には、高さ約4メートル、幅約8メートルもの大樋焼でできた陶壁などもある。工芸や美術が好きな人には、金沢駅内の散策も楽しくなります。
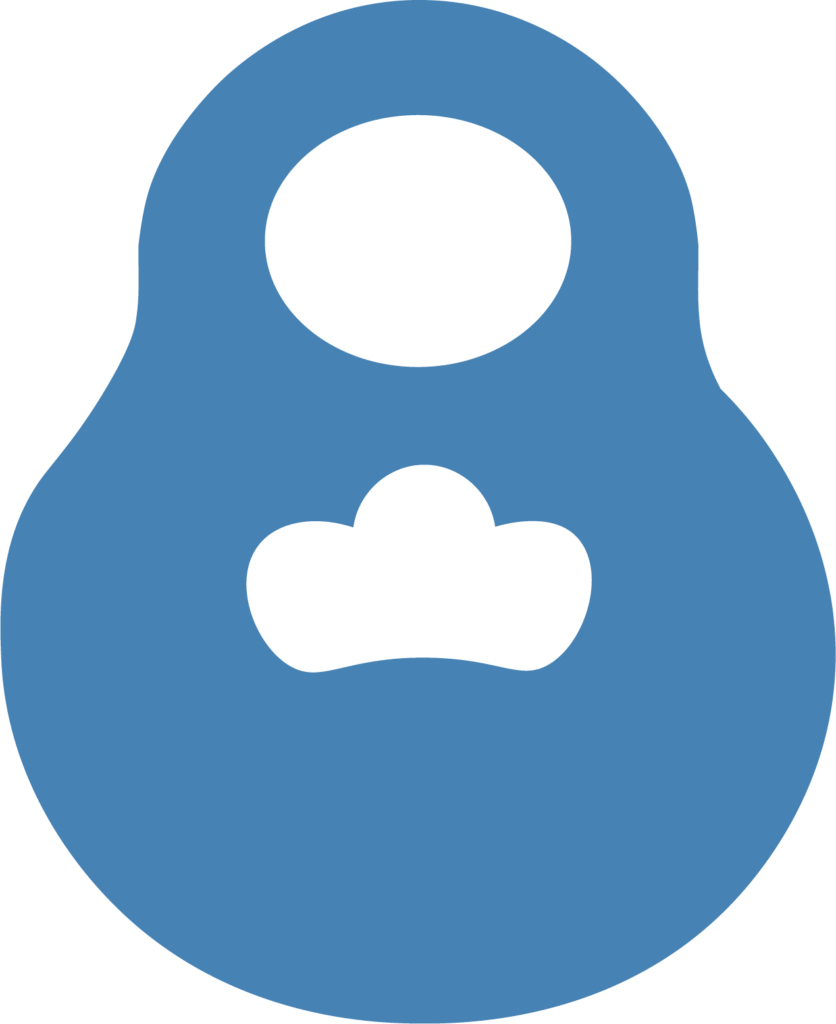
出発前も伝統工芸鑑賞

出発時間を少し早めて、改札内で余韻の伝統工芸鑑賞。まずは、新幹線改札すぐの柱。ガラスでできた一般的な柱に見えるが、よく見ると伝統的な和紙を使った柱になっている。そして、中2階に上がると目の前の時刻パネルやトイレに目が行きがちだが、ここにも伝統工芸がある。時刻パネルの下には、金沢の二俣町で作られる二俣和紙、左右には加賀友禅が並んでいる。

左手にある待合室に入ると、小さな丸がいっぱい。そのひとつひとつに加賀毛針、太鼓や加賀起上りなど、なんと236個もの作品があります!好きな人には出発までには見切れないかも。最後に、新幹線のプラットホームにある柱を見上げて見て。柱上部には本物の金箔が使用されており、最後に金沢を感じる場所でもあり、金沢に到着したときも最初の金沢が感じられる場所です。
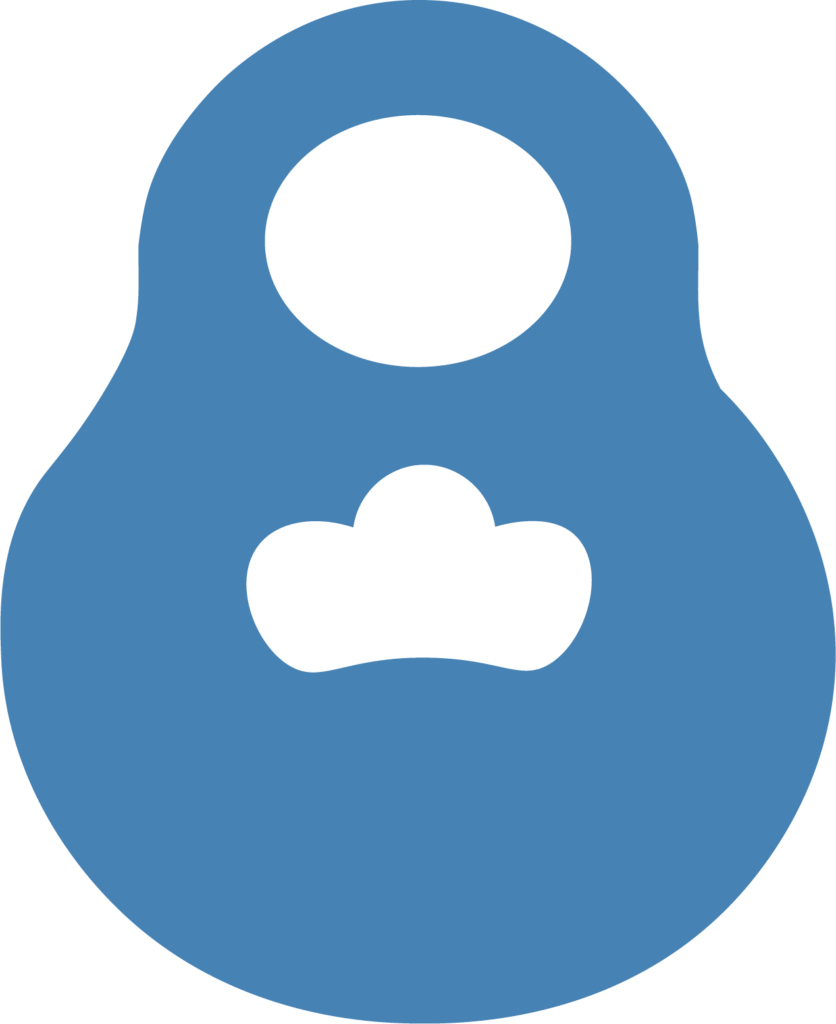
最後に
駅というのは、あくまで途中地点であり、注目することない場所。しかし、金沢駅は途中地点ではなく、目的のひとつにもなっている場所。その代表が鼓門ともてなしドーム。だが、そんな途中地点の場所にまで伝統工芸があり、まるで美術館のような駅が金沢駅。工芸王国石川が随所に感じられる魅惑の金沢駅をぜひ堪能してみてください。また、石川県公式の紹介サイトもあり、製作者のコメント付きなので、サイトを見ながらの散策もおすすめ!(石川県公式金沢駅伝統的工芸探訪ガイド)
DETAILS 詳細
金沢駅
かなざわえき

石川県金沢市木ノ新保町1-1



OTHERS 他